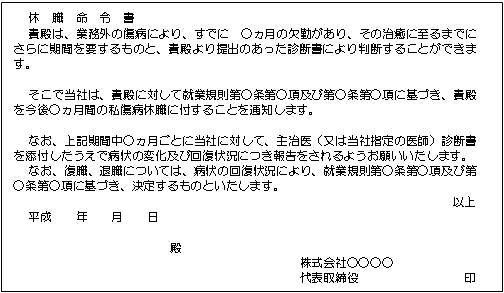第57回 (平成18年11月号)
通勤災害で脊髄を損傷した社員を解雇できるか?
休職期中の社会保険料は!?
通勤災害で脊髄を損傷した社員を解雇できるか?
休職期中の社会保険料は!?
SRアップ21広島(会長:守屋 薫)
相談内容
3ヶ月前のこと、V社のT社員がオートバイで通勤中に転倒し、脊髄損傷の大けがを負ってしまいました。即入院で、現在も入院中、全治ははっきりとしませんが、1年間は療養が必要で、その後も車いす生活になるだろうというような状態です。事故直後のV社は蜂の巣をつついたような大騒ぎで、お店も臨時に2日間休業し、病院や監督署、T社員の田舎の両親の出迎えなど、とW夫妻は疲労困憊したものでした。最近はやっと落ち着きを取り戻し、新たな調理師も採用してお店も順調になってきたところです。
「そろそろT君に退職の話をしないとなぁ…、社会保険料も3ヶ月分たまっているし…そうそうお見舞いにもいけないし…言いにくいなぁ…」とW社長、「いつまでもこのままじゃだめよねぇ…」と奥様が返します。なんとも結論が出難い話を延々としたW夫妻は、意を決してT社員が入院する病院へ出向くことにしました。回りくどい話をしながら、やっとのことで退職の話を切り出すと、「やはりそうですか…病室の仲間から解雇されるよ、って言われましたよ…でもこんな状態でV社をやめたくないです。せめて、退院してから将来の話をしたいんです…」とT社員が泣きながら訴えると、W夫妻は居たたまれなくなって逃げるように病室を後にしました。
「困ったなぁ…」とW夫妻が頭を抱えているところに、T社員の父親から電話がありました。“息子を見放さないでくれ”、という内容の長電話にますます消沈するW夫妻にさらに追い討ちがかかりました。なんとT社員の彼女であるお店のパートのA子(1日8時間勤務・週5日出勤)が妊娠しているという他の社員からの情報が舞い込んできたからです。
相談事業所 V社の概要
-
- 創業
- 昭和59年
- 社員数
- 3名(パートタイマー 9名)
- 業種
- 飲食業
- 経営者像
中華料理店を営むV社は、W夫妻が中心となってお店を切り盛りしています。“スープが旨い”という評判で、創業から21年、これまでに2人の社員を独立させました。社員3名はいずれも調理師です。経営的に苦しいながらも社会保険には加入しています。
トラブル発生の背景
V社は小規模の飲食店ですから、就業規則も何もありません。まさかこのような大事件が発生するなどとは夢にも思っていませんでした。
気のよいW夫妻には荷が重過ぎる事件だと思いますが、何とかしようにもその方法が皆無でした。
経営者としての判断と人間としての情実に板挟みになっているようです。
経営者の反応
「社長、T君はどうなるのですか?」とF社員が質問してきました。「それがわからないから、イライラしているんだ」とW社長が怒鳴りつけると「彼女に子供ができたのに、自分は病院で寝たきりなんてかわいそうですよね、もしかしたら、僕らも何時ケガするかわかりませんし、気になるのですよ。あっそうそう、A子が社会保険に入りたいと言っていましたよ、これまではいくら言ってもだめだったのに、子供ができた途端に変わるんだから、しっかりしていますよね…」とF社員から言われてしまいました。その後はお店が忙しくなり、W社長は何とか一息つきましたが、「今日は味がおかしいね」というような苦情が顧客から多発し、W社長は青くなりました。「お店…いや、会社としてどこまで責任があるのか、まずはそれから調べよう。このままじゃT君と共倒れになってしまう…とてもじゃないが、ご両親や彼女のことまで責任負えないよ…」という点でW夫婦の意見が一致し、相談先を探し始めました。
弁護士からのアドバイス(執筆:足立 茂樹 )
T社員は1年間の療養が必要で、その後は車椅子生活になる見通し、V社は新しい調理師を採用し、店も順調とのことです。?社がT社員を解雇せざるを得ないと思うのは当然のことでしょう。
さて、労働基準法第19条は、業務上の負傷にかかる療養休業中の解雇を禁止しています。本件にこの規定が適用されるでしょうか。
同条での「業務」とは当該事業の運営にかかわる業務であって、当該労働者が従事するものをいいます。T社員はオートバイで通勤中に転倒したわけですが、この通勤は業務とは密接な関連性をもっていますが、一般的には事業主の支配下にあるとは言えません。よって、本件にこの規定の適用はありません。
たとえば、T社員が通勤の途中で業務(例えば、仕入れ)を行っていたような場合は、「業務の性質を有する通勤」にあたり、療養休業中の解雇は禁止されることになります。
次に、労働基準法第19条が適用されない場合、?社はT社員を解雇できるのでしょうか。解雇予告義務(労働基準法第20条)を果たせば、民法上は、雇用期間の定めが無い場合は何時でも、雇用期間の定めがある場合でもやむを得ない場合は、直ちに解雇できることになっています(民法628条、629条)。
しかし、「解雇権濫用の法理」が判例上確立しており、「当該具体的事情の下において、解雇に処することが著しく不合理であり、社会観念上相当なものとして是認することができないときには、当該解雇の意思表示は、解雇権の濫用として無効になる」とされています(最高裁判決昭和52・1・31、その他判例多数)。昨今の解雇に関する相談の多くは、この解雇権の濫用に当たるかどうかというものです。
本件の場合、業務性がないということであれば、T社員は1年間の療養が必要で、しかも車椅子生活になる見通しであり、職場復帰が困難という事情からすれば、解雇が著しく不合理とはいえないと思われます。一方、業務性が認められる場合、例えば、T社員が通勤の途中で仕入れ業務をしていたような場合は、事故の責任の有無、経営上解雇の必要性の有無・程度、退職金の有無等を総合判断することになるでしょう。
また、T社員の勤務形態、勤務時間によっては、過労が事故の原因となったという場合もあるかもしれません。その場合は直ちには解雇できなくなるケースもあります。
このように直ちに解雇できない事情がある場合には、いったん「休職」させたうえで再度解雇の可否を考えてみるべきでしょう。
社会保険労務士からのアドバイス(執筆:谷 宏男)
V社にかかわらず小規模事業所においては、就業規則を定めていないことが多々あります。何事もないときはよいのですが、本件のように就業規則が存在しない状態でトラブルが発生すると、その解決が長引き、しかも困難を要する結果となってしまうのです。
本件解決方法については、最大1年位までの病気休職期間を設けることをV社とT社員が話し合い、T社員が安心して療養に専念できる環境をつくることを勧めます。
そして、休職期間が満了する1ヶ月前に再度話し合い、そのときの状態で職場復帰が難しいということになれば、退職に向けた話し合いをすることになります。
T社員は脊髄損傷で車椅子状態になるかもしれないということですので、療養期間がかなり長期化する恐れがあります。1年の休職期間を適用しても復職は不可能と医学的に認められる場合は、これも話し合いの上、休職制度を利用しないで退職を選択する可能性もあります。この選択肢を選ぶ理由は、退職後も労災保険の給付を受ける権利は変わらないこと、社会保険料の自己負担がなくなること(国民健康保険・国民年金に加入)、休職期間中の賃金支給がないことなどが挙げられます。
本件はT社員のみならず、V社の他の社員に与える影響も大きいと考えられますので、“会社の姿勢をどう見せるのか”という点を含めて慎重に対処する必要があると思います。
次に諸手続についてご説明します。
本件は交通事故でも加害者がいない自損事故となりますので、労災保険の給付(通勤災害)を受けることになります。療養給付、休業給付はもとより、万が一障害が残れば、障害給付の請求をすることとなります。V社は必要に応じて、T社員の労災保険給付請求手続に関するサポートを行わなければなりません。
社会保険については、休職していても会社との雇用関係は継続していますので、毎月の健康保険料、厚生年金保険料が徴収されます。この社会保険の本人負担分保険料は、T社員から毎月会社に振り込んでもらう(あるいは現金で預かる)方法がよろしいと思います。何事も“溜めてしまう”と大変です。面倒でも月々徴収しておきましょう。
場合によっては、月々の社会保険料相当額を「休職期間中の賃金」とすることもできます。支払われる賃金が平均賃金の60%以下であれば、労災保険の休業給付を全額受給できますので問題ない額です。
今後は、V社でも就業規則を作成し、 (1)休職事由 (2)休職手続き (3)休職期間 (4)休職中の処遇 (5)復職手続き (6)休職期間満了時に職場復帰できない場合の取り扱いを定めておく必要があると思います。その際には、本件でT社員に示した以下のような休職に関する条文をドラフトとして活用してください。
■休職とは
休職について公務員は国家公務員法79条、地方公務員法28条に定められていますが民間企業には法的規定がありません。
休職とは、従業員の側において就労することが不能または不適切な事由が生じた場合に、一定期間雇用の義務を免除するまたは禁止することをいいます。
休職の種類
1. 従業員の都合によるもの
(1) 傷病休職
(2) 自己都合休職
(3) 公務休職
(4) 組合専従休職
2. 会社の都合によるもの
(1)出向休職(業務命令とする休職)
(2)起訴休職
3. その他
(1) 労災休職
(2) 伝染病休職
■休職期間前の欠勤許容期間(休職を発令する要件)
休職に入るかどうかは従業員が使用者から命じられた業務ができるかどうかによって決められます。一般的には就業規則で先に傷病欠勤した後、休職の発令となります。その発令の日が休職期間の起算日となります。
(休職)
第○条 従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として休職を命ずる。
(1)業務外の傷病のため,引き続き3ヵ月を超えて欠勤したとき
(2)自己の都合による欠勤が、引き続き1ヵ月を超えたとき
(3)公職に就任し、公務のため勤務ができない日が1ヵ年を通じ130日を超えると認められるとき
(4)会社の命令により、関係会社又は関係団体の業務に従事するとき
(5)その他前各号に準ずる程度の事由があるとき
■休職に関する書式
■休職期間
休職期間は各企業ごとに定めることができ、特に法的な制限はありません。従前の勤務実績に応じて一定の期間を定めるという方法がよくみられます。
従業員は就業規則に規定されている休職期間以上のものを請求することはできません。
一般的に大企業は休職期間が1年から3年くらいですが、小規模事業場では3ヵ月から6ヶ月が多いようです。
(休職期間)
第○条 前条の休職期間は次のとおりとする。
(1) 前条第1号のとき
勤続期間5年未満の者 3ヵ月
勤続期間5年以上10年未満の者 6ヵ月
勤続期間10年以上の者 12ヵ月
(2) 前条第2号のとき 2ヵ月
(3) 前条第3号から第5号までのとき 必要な期間
2 前項第1号及び第2号の場合、通算2年間を限度として延長することがある。
■復職及び退職
休職期間満了日に復職できない場合を解雇としている場合と休職期間満了日に復職できない場合を退職としている場合があります。一般的には退職としている場合が多いと思います。「休職期間満了時において、なお休職事由があるときは自然退職とする」と明確に規定しおくのが望ましいでしょう。
また休職期間満了時に完全に心身が戻らないで、後に比較的短期間で完全に就労が可能となる場合などは、短時間勤務・軽作業を組み合わせて職場復帰プログラム的な段階的復職を採用するケースもあります。
さて、T社員の彼女であるパートのA子さんですが、1日8時間勤務の週5日出勤ですので現状では社会保険に加入させなければなりません。
まず健康保険と厚生年金保険ですが、一般社員と比べて、(1)1日または1週間の所定労働時間がおおむね4分の3以上であり、かつ(2)1ヵ月の所定労働日数がおおむね4分の3以上の人は、加入させなければなりません。
また、雇用保険については、1週間の所定労働時間が30時間以上の人については、一般被保険者として加入させなければなりません。1週間の労働時間が30時間未満の人で?週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 (2)1年以上の雇用が見込まれること、の要件を満たす場合は、短時間被保険者として加入させなければなりません。
A子さんの場合は、被保険者資格を充たした時期(入社したときからの場合は入社日)に遡って資格取得手続を行なう必要があります。
税理士からのアドバイス(執筆:西山 健三)
本件の場合、V社が取るべき道は普通であれば次の2つと考えます。
(1)T社員には退職してもらう、あるいはやむなく解雇。(V社とは縁が切れる)
この場合、近い将来回復した場合には相談のうえ復帰もあり得る前提で退職してもらうことも考えられますが、一旦退職することには変わりないので税務上の扱いに違いは出ません。
(2)当面V社には在籍して療養の状況を見守る。(V社としてはその間の給与は支払えない)
それぞれに労働基準法等の法的な扱いなど色々あるでしょうし、これら以外の解決法もあるかもしれませんが、ここでは以上のケ?スに絞って税務上の扱いを説明します。
その前に、いずれのケ?スにも共通して考えられるT君への税金の扱いを説明します。
まずT社員が健康保険や労災保険から受ける様々な給付ですが、これらは非課税となります。(健康保険法第62条同第149条、労働者災害補償保険法第12条の6)
また、T社員が職探しをする場合、職業安定所から受ける失業給付も同様に非課税です。(雇用保険法12条)
次に、T社員が自分で生命保険会社などの医療保険等に加入していて、そこから保険金が出る場合(よくある入院1日当たり1万円とかいう商品などです)も非課税です。(所得税法第9条1項16)
さらに、仮に今回のオ?トバイ事故に他の当事者がいる場合(例えば乗用車との衝突事故など)で、その相手もしくは相手の加入している自動車保険から賠償金が出る場合も非課税ですし、自分が加入している自動車保険から保険金が出る場合も同様です。(同所得税法)
T社員が受け取る見舞金(V社からのものも含む)も同様に非課税。(同所得税法)
このように、事故に遭ったことにより本人が受ける様々な給付等については、概ね税金はかからないことになります。
それでは、最初に挙げた2つのケースに分けて考えてみましょう。
(1)T君が退職(解雇を含む)する場合ですが、会社に規程に基づく退職金制度が有るか無いかは別にして、今までの貢献を考え、または今後のT社員への支援の意味も込めて退職金を支払ったとします。
これは退職所得としてT社員に課税されますが、退職所得の場合勤続20年以下は1年につき40万円、20年を超えた部分は1年につき70万円の退職所得控除があります。(所得税法30条)
つまり例えば勤続10年なら400万円まではT社員に税金がかかりませんので、通常中小企業が支払う退職金に関しては、受け取った社員に税金がかかることは少ない訳です。
もちろん、退職した事実に起因して退職金として支払うことが必要であり、例えば臨時賞与とか特別見舞金とか言う名目にするのは避けましょう。さらに、退職金として支払ったことに関しての税務上の書類も必要になってきます。ちなみに解雇予告手当も税務上は退職所得になります。(所得税法基本通達30-5)
会社側の税務上の扱いですが、もちろん損金算入(つまり経費として落ちる)です。
役員や社長の同族関係者に対する退職金については税務上会社の損金にならない部分が出る可能性もありますが、本件の場合はその心配は無いでしょう。
ところで、会社が退職共済等に加入していた場合で、共済等からT社員に退職給付が支給される場合もT社員にとっては退職所得であり、税務上の扱いは同じです。
(2)当面V社には在籍して療養の状況を見守る場合ですが、V社としてはその間の給与は当然支払えませんから、V社としてはその間の社会保険料の負担や見舞金の支払に税務上の判断が出てくるくらいです。
いずれも会社の損金算入ですが、見舞金については出来れば慶弔見舞金規程を作っておき、その範囲内の金額とするのが望ましいといえます。
社会保険料については、社会保険料を控除する給料が無い訳ですから、本人負担分も一旦は会社が立て替えると思いますが、もしも、その立替が溜まってしまい、結局本人からもらえずじまい(よくある話です)の時はどうなるのでしょうか。この場合は、最後は、給与または退職金として会社の損金にすることになるります。
最後に、今回のように事故が起きてしまった後では、会社に出来ることに限りがあります。しかし今後については、このような事故に何らかの備えを行うことは出来ると考えます。最も手っ取り早いのが民間の生保・損保の傷害保険等に加入することです。掛け捨てで、従業員が総体的に若い場合はさほどの負担にはならないはずです。もしもの時はその保険金を本人に退職金(見舞金の場合もありますが)として渡すことが出来ます。
社会保険労務士の実務家集団・一般社団法人SRアップ21(理事長 岩城 猪一郎)が行う事業のひとつにSRネットサポートシステムがあります。SRネットは、それぞれの専門家の独立性を尊重しながら、社会保険労務士、弁護士、税理士が協力体制のもと、培った業務ノウハウと経験を駆使して依頼者を強力にサポートする総合コンサルタントグループです。
SRネットは、全国展開に向けて活動中です。
SRアップ21広島 会長 守屋 薫 / 本文執筆者 弁護士 足立 茂樹 、社会保険労務士 谷 宏男、税理士 西山 健三